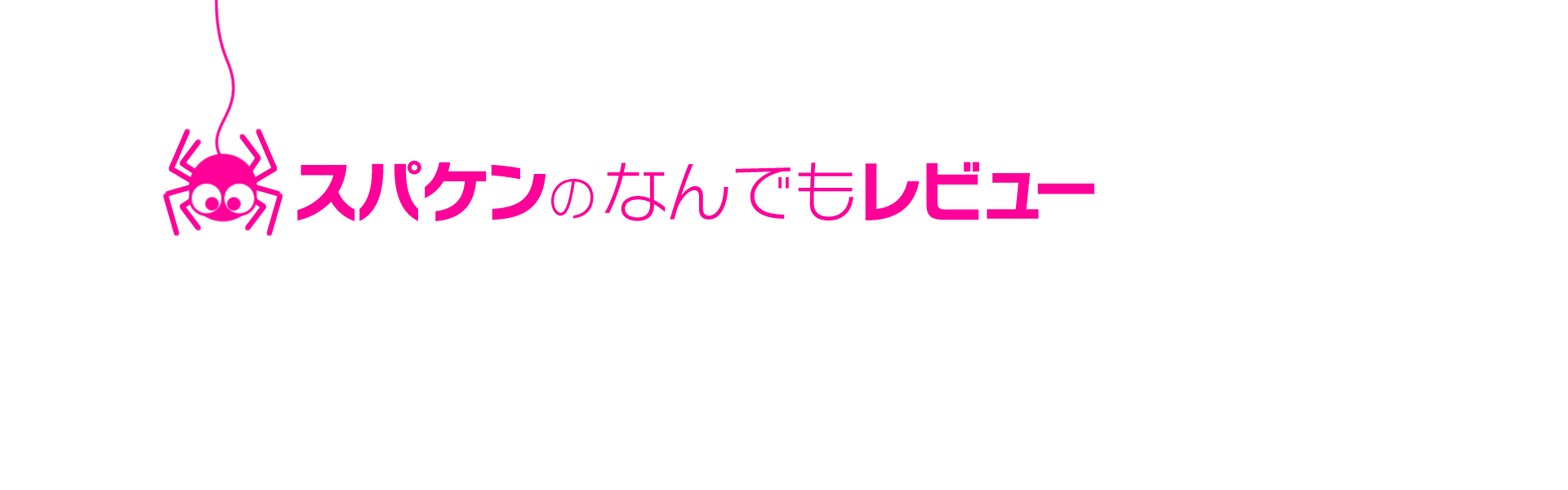泣いているのはウルトラマンだけではない「ウルトラマンが泣いている」
「ウルトラマンが泣いている ―円谷プロの失敗」(円谷 英明)を読んだ。

なんということか・・・
小説で救われない話を読むことはあるが、これは本当の話だ。
読み終わった後の後味の悪さは、想像以上だった。
泣いているのはウルトラマンだけではない。
ファンが泣いている・・・
そして、子どもたちが泣いている・・・
円谷英明って誰?
ウルトラマンファン、特撮ファンはもちろん、それ以外の人でも円谷英二の名前を知っている人は多いだろう。
「ウルトラマン」シリーズなど、特撮作品を作った円谷プロの初代社長が円谷英二だ。
では、この著者の円谷英明って誰?
- 円谷英二【初代社長】(1901年7月10日〜1970年1月25日)
- 一 [はじめ]【二代社長】(1931年4月23日〜1973年2月9日)
- 昌弘【五代社長】(1957年〜)
- 英明【六代社長】(1959年〜)
- 浩 [本名:寛](1964年3月4日〜2001年7月24日)
- 皐 [のぼる]【三代社長】(1935年5月10日〜1995年6月2日)
- 一夫【四・八代社長】(1961年〜)
- 粲 [あきら](1944年〜)
- 一 [はじめ]【二代社長】(1931年4月23日〜1973年2月9日)
円谷英二の長男であり、二代社長の円谷一(はじめ)の次男が円谷英明だ。
だから、この本はすべて円谷英明の視点で書かれている。
円谷一夫の視点では、また異なった話になるかもしれない。
そこを理解した上で読まなければいけないと思う。
初代社長・英二、二代社長・一について
模型作りなどに長けた技術畑の祖父・英二、芸術家肌の演出家だった父・一については、短く、アッサリと書かれている。そして、悪くは書かれていない。
ただ、技術畑、芸術家肌という表現でなんとなく感じると思うが、この頃から経営についてはあまり得意ではなかった様子がうかがえた。
ウルトラマンがヒットしていたこともあり、よく言えば大らかな時代だったのだろう。
ただ、企業としてはまだ未熟と言われてもしょうがない状態だった。
諸悪の根源(?)三代社長・皐
ここで三代社長の皐(のぼる)の登場。
ここから憎悪が込められた文章が延々と続く。
とにかくワンマンで、独裁的なやり方で、考えているのは己のことだけみたいに描かれている。
読んでいると、こちらまで怒りがふつふつと湧いてきた。
三代社長になり、物事の判断基準が「よい作品を作るために」から「己のために」になってしまっているので、うまくいくはずがない。
豪邸を買い漁ったり、私利私欲にまみれていく様は、読んでいて腹立たしく感じた。
さらにまわりもイエスマンばかりで、横領するヤツもいたりして、読むのがイヤになってくるほど。
この頃もまだ杜撰で計画性がなく、何百万円ものボーナスを出すかと思えば、大規模なリストラを行ったりと、まだ普通の企業とは同じように語れる状態ではなかった。
また、社外に対して不遜な態度を取って絶縁状態になったり、クリエイターたちへの態度は敬意を払っているようには感じなかった。
調子がよい時はそれでも、まわりはついてくるかもしれない。しかし、そんなことをしていると、いつか愛想を尽かされるのは目に見えている。
終わりの始まり
昌弘、英明が社長になり、ようやくマトモになりかけ、経営も立て直しかけたと思われたが、四代社長・一夫が社内クーデターで返り咲く。
一夫は三代社長・皐(のぼる)の長男だ。
ここでも一夫は会社よりも、自分の地位を守ろうとする。
そして、結局、外部資本によって乗っ取られてしまう・・・
最初はちょっとしたボタンの掛け違いだったものが、あとあとジワジワと首を絞めていく。
例えば、ちょっとした契約のミスで複雑な著作権が絡んでしまい、海外に進出できなくなってしまった。
こんなこと考えてもしょうがないとはわかっていても、あそこでこうしていれば・・・みたいなことを考えずにいられなかった。
ただ、読んでいて思ったのは、ウルトラマンなど30分間の特撮番組の制作だけでは採算があわないということ。
テレビ番組の予算より、どうやっても制作費の方が高くなってしまう。予算内に収めると、見劣りのする映像になってしまう。だから、番組を作れば作るだけ赤字が増えることになる。
平成三部作と言われる「ウルトラマンティガ」「ウルトラマンダイナ」「ウルトラマンガイア」でも大赤字だったらしい。
制作費の赤字をキャラクターを使ったマーチャンダイジングで黒字にすれば・・・と考えたりしたのだが、売れるのはテレビ放映中だけで、残ったものは売れないらしい。
そういえば、仮面ライダーも、戦隊ヒーローも、おもちゃ売り場は毎年入れ替わっている。
そう考えると、ディズニーやピクサー、ジブリのキャラクターはスゴい。
同じように、残り続けるキャラクターを作らなければいけなかったのだろうが、結局、残っているのはクラシックウルトラマンくらい。これだけではやっていけない。
特撮と、CGと
時代の移り変わりとともに特撮からCGに変えていく手もあっただろう。
でも、最初にこんなことが書かれていた。
当時の特撮は、CG(コンピュータ・グラフィックス)に慣れた今の視聴者から見れば、ちゃちな子供だましと言われるかもしれません。ただ、これだけは言えます。特撮にはでこぼこした手触り感があります。それは実物だけが持つ迫真です。どう壊れるかはやってみなければ誰にもわかりません。作った人が、こうなるだろうと考える決めつけを、あっさり裏切ります。全能ではない生身の人間と、なかなかその思いに応えてくれない素材が織りなす、結果が予想できないドラマです。
そう。僕も特撮が好きだ。
円谷プロが特撮をやめて、CGだけになってしまっていたら?
生き残ったかもしれない。でも、それなら円谷プロじゃなくてもいいような気もする。
30分番組じゃ採算が合わないなら、2時間の映画ならできたのではないかと思った。
「ILM」(Industrial Light & Magic)のような、特撮の専門のスタジオにして、世界中の映画の特撮を請け負うなんてステキやん。と思ったけど、今時、みんなCGで作ってしまうから、特撮なんて必要ないのか・・・
つまらない内輪もめで首を絞めていったけど、結局、特撮はお金と手間がかかるので、もっと安く制作できるCGが登場してしまった今となっては、必要がなくなった技術なのかもしれない。
最後に・・・
2006年、英明は上海に制作会社を設立し、特撮ドラマ「五竜奇剣士」を制作する。
上海の撮影スタジオに機材を持ち込み、現地のスタッフでは制作できないことがわかると日本からもたくさんのスタッフを呼び、撮影を始めた。
しかし中国という国独特のルールに縛られてしまう。
申請に時間がかかるなど当たり前、この時は半年待たされたらしい。
さらに週1回30分番組1年分(52本)の撮影を半年で行わなければいけない(半年過ぎると再申請でまたまた時間がかかる)という。
9話まで撮影した時点で、資金がつきてしまい、2008年、ついに自宅を売却してしまう。
そして、52話から13話に減らし、完成を目の前にする。
しかし、ここでもまた一筋縄ではいかない中国ビジネスの落とし穴が待っていた。
なんと業務委託していた中国の編集会社が反乱を起こす。
ハードディスクに収めたすべての映像素材を押さえてしまい、主張する条件を飲まなければ使わせないという、もうわけのわからない世界。
自分たちが素材を押さえているのだから、勝手に編集し、番組にして売ることができると言ってるらしい。
さすが、著作権もなければ、映像の所有権もない国、中国。
その主張する条件というのが、52話分の業務委託料を前払いすることだった。当然52話分は出せないので、13話分で収めるように交渉したらしいが、聞く耳を持たず、そうこうしている間に会社の運営資金は底を突いてしまう。
なんなんだ、このバッドエンドは?
最後の文章を読むと、泣けてくるのは僕だけではないはずだ。
私は今、映像の世界からは完全に足を洗い、ブライダル会社の衣装を運ぶ仕事で忙しく働いています。日々、淡々と過ごす中で、唯一の楽しみは、かつて円谷プロの若いスタッフたちと共に、よく父に連れていってもらった海釣りです。
未明のうす暗い海で、ひとり静かに釣り糸をたれていると、私が子供だったころの円谷プロのスタジオの、華やかなりし日々の喧騒が聞こえてくるのですが、あるいは、打ち寄せる波の音が、そう聞こえるだけなのかもしれません。
- ←前の記事
- リアルな「ウルトラQ」ではない「MM9」
- 次の記事→
- おもしろい本を読みたい。東野圭吾「手紙」